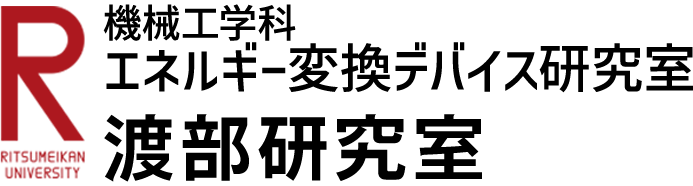学生のみなさんへ
はじめに
当研究室は2021年度に設立されました.最近のエネルギーのニュースを見ると,二酸化炭素の排出を抑えた社会が目標になっており,脱炭素社会やカーボンニュートラル社会などの用語が使われています.脱炭素,と言われてますが,炭素は我々の社会に必要であり,炭素資源はエネルギーの安定供給に欠かせないのが現状です.社会が求めているコンセプトは,二酸化炭素の排出と吸収のバランスが取れた炭素循環にあります.燃料電池/電気分解システムは、燃料が有する化学エネルギーと電気エネルギーを相互変換できる可逆的な特性があり、循環型社会に適合した特性を持ちます。また,多様な資源から製造できる水素も炭素循環に欠かせないエネルギーです.当研究室では,燃料電池・電気分解・水素生成などのエネルギー変換デバイスの研究を進めています.
デバイスを設計するためには,そのデバイスの中でどんな現象が起きているか知る必要があります.エネルギー変換デバイスの核となる電極や触媒を設計するときも同じです.現象を「観察」して設計方針を考えます.電極触媒の性能や機能においては,マクロレベルの構造よりも,欠陥などの原子レベルの局所構造の方が重要なケースがあります.当研究室では,実験科学を主体としつつ,第一原理計算などの計算科学も併用し,原子スケールからマクロスケールに至るマルチスケール観察と「ものづくり」をコンセプトにしています.
研究室の方針
大学生活で,一番面白いのは研究だと思います.研究の面白さは,課題を発見し,アプローチを考え,挑戦し,世界で初めての新しい結果を発見することにあると思います.研究が成功し,その結果が社会に還元できれば,とても良いことだと思います.うまくいかなかった場合も,自分で考えたアプローチは残ります.修正して,また挑戦すればよいと思います.
アクティブな研究活動は,実験や数値シミュレーションのハードスキルだけでなく,企画力,チームワーク,リーダーシップ,国際性といったソフトスキルも向上させることができます.学生のみなさんが主体的に研究を進め,研究の過程で直面する様々な問題に対し,周囲とのコミュニケーションや,問題解決のための手段を試行錯誤する思考力,行動力を育み,社会で活躍できる基本能力を高められる研究室を目指しています.
学ぶときは学び,遊ぶときは遊ぶ,メリハリのある研究生活を送ってほしいと思います.研究は時間がかかります。思った通りに進まないこともよくあります.気が乗らないときは実験台を片付ける程度で十分です.大事なことは続けることです.楽しくやると,続きます.面白い成果も出てきたりします.なので,楽しく進めることをモットーにしています.ひとりひとりが研究テーマと真摯に,謙虚に向き合うことを期待しています.
研究室生活について
配属後、教員と相談して研究テーマを決定します。各自で目標を設定し、スケジュールを組んで研究に取り組みます。ゼミは週1,2回程度、他にも、月2,3回程度の雑誌会があります。個別打ち合わせは随時行います。コアタイムはとくにありません。みなさんの自主性を尊重します。以下,大体の年間スケジュールです.
4月 春ゼミスタート,歓迎会
7月 中間発表,中間発表お疲れ様会
8月 夏休み
9月 秋ゼミスタート,OB会
12月 研究発表会,忘年会
1月 冬ゼミスタート,研究ラストスパート,引継ぎ(~3月)
2月 卒業研究発表
3月 春休み
本研究室に興味のある方は、随時見学可能です。研究内容や研究室生活など、なんでも聞いてください。